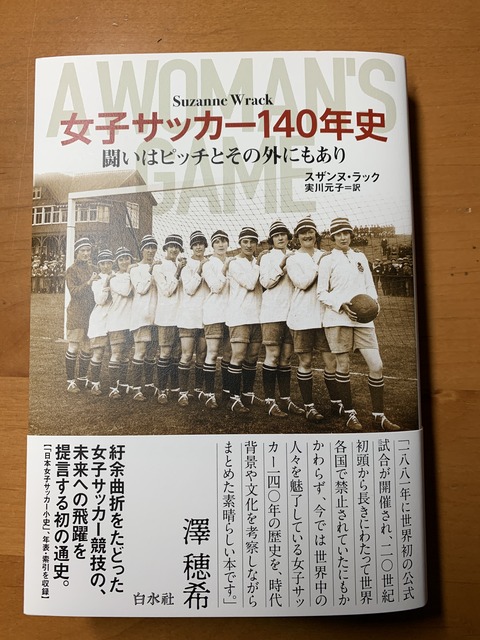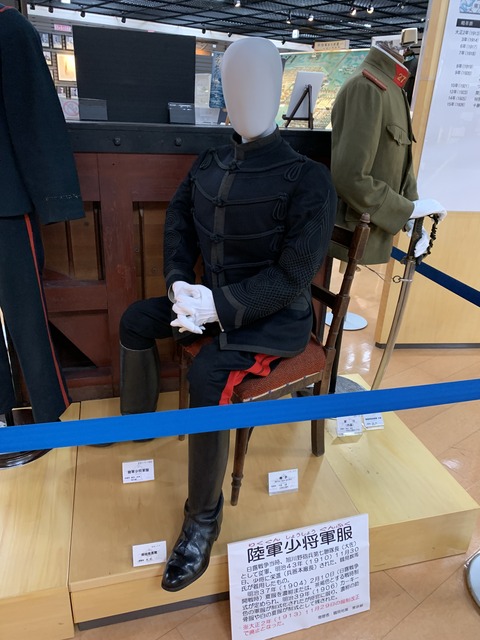今年は11月まで締め切りに追われに追われて、腰を据えて本(学術書みたいなの)を読むことがなかなかできなかったのですが、就寝前に読み耽ったお楽しみ本(漫画)はいろいろとありました。
シリーズで読み耽ったのは、
アン・クリーヴスのシェトランド島シリーズ(昨日、ついにシリーズ最後となる「炎の爪痕」が出てしまって、これ読み終わったらもうペレス警部に会えなくなるのかと思うとさびしくなるから読めません)
あさのあつこの弥勒シリーズ(「闇医者おえん秘録帖」「ラストラン」「バッテリー」にも)
ドラマにもなった「アンサング・シンデレラ」(まだ終わりそうにないのがうれしい)
8年にわたる連載が終わった「ゴールデン・カムイ」
でした。
お楽しみ本にハマるのは、私の場合、現実逃避したいときで、だからできるだけ自分がいまいる環境とは異なる場所や時代が舞台になっているものを選ぶ傾向にあります。
そのためか、北欧やアフリカを舞台にしたミステリー、サスペンスとか、時代小説がハマるのにぴったり。
お楽しみとは言えないのだけれど、「障害」に関する本にも結構はまりました。
自分が年齢を重ねているうちに身体的・頭脳的にいろいろとできなくなることが増えてきて、この不具合(dysfunction=機能障害)やできなくなること(disability=能力欠如)を自分にどう納得させてつきあっていけばいいのか。またそういう「障害」による社会的な不利益=handicapをいかに減じていけばいいかを考えたかったから。
伊藤亜紗さんの「目の見えない人は世界をどう見ているのか」(光文社新書)を数年前に読んでほほ〜と目を見開かされて以来、「記憶する体」「目の見えないアスリートの身体論」「わたしの身体はままならない」とか立て続けに読みました。そもそも自分の身体を自分が思うように動かせられるものなのか。ままならない身体をAIがどこまでサポートできるのか。認知症で骨粗しょう症の母の身体を見ながら、将来自分が老いていく姿を想像し(でもたぶん9割がた外れているだろうけれど)、dysfunctionalでdisableになることを受け入れられる力を養っています。
ベストセラーになった「目の見えない白鳥さんとアートを見にいく」(川内有緒)もたいへん示唆に富む、そしてたのしい本で、「視る」ことで成り立っていると思っていたアートの鑑賞を根元からくつがえしたし、そうかそういう楽しみ方、「見方」もあるのかと目からウロコ本でした。
「くろは おうさま」(メネナ・コティン文・ロサナ・ファリア絵 うの かずみ訳)は視覚障害を持つ人のための絵本で、さわることで楽しめるという、これまた目からウロコでした。編集した細江幸世さんと訳者の宇野和美さんのトークイベントもたいへん興味深かった。点字で読書する視覚障害者が3割くらいしかいないっていうのも驚きだったし、dysfunctionやdisabilityがある人たちのアートのことを知ってわくわくしました。そして何よりも、この絵本が見て美しく、さわっても美しいことに驚きです。
まさに機能障害や能力欠如を社会的不利益にしないことのヒントが詰め込まれていたのが 「みんなが手話で話した島」(ノーラ・エレン・グロース著 佐野正信訳 早川書房)でした。アメリカ合衆国マサチューセッツ州にあるマーサズ・ヴィンヤード島では20世紀はじめまで聾唖者が多く、島民は健聴者であっても手話でお互いのコミュニケーションをとっていたそうです。その生活があまりにもノーマルだったので、調査した著者が「家族や知り合いに聾者がいましたか?」と聞いても、思い出せないお年寄りも多かったとか。dysfunctionがhandicapではなかったという話は、これから超高齢化を迎える日本社会において障害をいかにハンディキャップにしないかとうヒントが詰まっているのではないかと思いました。
シリーズで読み耽ったのは、
アン・クリーヴスのシェトランド島シリーズ(昨日、ついにシリーズ最後となる「炎の爪痕」が出てしまって、これ読み終わったらもうペレス警部に会えなくなるのかと思うとさびしくなるから読めません)
あさのあつこの弥勒シリーズ(「闇医者おえん秘録帖」「ラストラン」「バッテリー」にも)
ドラマにもなった「アンサング・シンデレラ」(まだ終わりそうにないのがうれしい)
8年にわたる連載が終わった「ゴールデン・カムイ」
でした。
お楽しみ本にハマるのは、私の場合、現実逃避したいときで、だからできるだけ自分がいまいる環境とは異なる場所や時代が舞台になっているものを選ぶ傾向にあります。
そのためか、北欧やアフリカを舞台にしたミステリー、サスペンスとか、時代小説がハマるのにぴったり。
お楽しみとは言えないのだけれど、「障害」に関する本にも結構はまりました。
自分が年齢を重ねているうちに身体的・頭脳的にいろいろとできなくなることが増えてきて、この不具合(dysfunction=機能障害)やできなくなること(disability=能力欠如)を自分にどう納得させてつきあっていけばいいのか。またそういう「障害」による社会的な不利益=handicapをいかに減じていけばいいかを考えたかったから。
伊藤亜紗さんの「目の見えない人は世界をどう見ているのか」(光文社新書)を数年前に読んでほほ〜と目を見開かされて以来、「記憶する体」「目の見えないアスリートの身体論」「わたしの身体はままならない」とか立て続けに読みました。そもそも自分の身体を自分が思うように動かせられるものなのか。ままならない身体をAIがどこまでサポートできるのか。認知症で骨粗しょう症の母の身体を見ながら、将来自分が老いていく姿を想像し(でもたぶん9割がた外れているだろうけれど)、dysfunctionalでdisableになることを受け入れられる力を養っています。
ベストセラーになった「目の見えない白鳥さんとアートを見にいく」(川内有緒)もたいへん示唆に富む、そしてたのしい本で、「視る」ことで成り立っていると思っていたアートの鑑賞を根元からくつがえしたし、そうかそういう楽しみ方、「見方」もあるのかと目からウロコ本でした。
「くろは おうさま」(メネナ・コティン文・ロサナ・ファリア絵 うの かずみ訳)は視覚障害を持つ人のための絵本で、さわることで楽しめるという、これまた目からウロコでした。編集した細江幸世さんと訳者の宇野和美さんのトークイベントもたいへん興味深かった。点字で読書する視覚障害者が3割くらいしかいないっていうのも驚きだったし、dysfunctionやdisabilityがある人たちのアートのことを知ってわくわくしました。そして何よりも、この絵本が見て美しく、さわっても美しいことに驚きです。
まさに機能障害や能力欠如を社会的不利益にしないことのヒントが詰め込まれていたのが 「みんなが手話で話した島」(ノーラ・エレン・グロース著 佐野正信訳 早川書房)でした。アメリカ合衆国マサチューセッツ州にあるマーサズ・ヴィンヤード島では20世紀はじめまで聾唖者が多く、島民は健聴者であっても手話でお互いのコミュニケーションをとっていたそうです。その生活があまりにもノーマルだったので、調査した著者が「家族や知り合いに聾者がいましたか?」と聞いても、思い出せないお年寄りも多かったとか。dysfunctionがhandicapではなかったという話は、これから超高齢化を迎える日本社会において障害をいかにハンディキャップにしないかとうヒントが詰まっているのではないかと思いました。